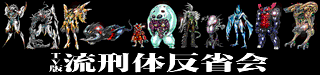
最終反省〜四天王篇(6〜最終話)
残心
「始まったら必ず終わる」〜あまりにも当り前な言葉だが、これは我が師匠である雨宮慶太カントクの言葉の中で、最もオレの身に染みたものである。その圧倒的大部分の用法としては「あぁ辛い。これはしんどい。もう死ぬかもしれない。いや細胞レベルでは半分以上死んでいる。ちっとも休んでない。休みたい。でもまだやらなきゃならない仕事が噴火山のように残っている。終わらない。どうしよう」という時に、パンドラの箱に残った最後の希望のようにこの言葉を思い返しては復唱し、ドーパミンを振り絞ることができる治癒系呪文のひとつ(ちなみにレベルが上がると『こっそりトイザらス』とか『バックレて温泉』なんかも使えるようになる)なのだが、ひとたび事が終わった「祭のあと」的な状況の中でこの言葉をくり返すと、不思議な感傷におちいることがある。それは必ず「ちゃんと終えることができたのか?」という自問から始まる。
オレは常日頃から無意識のうちに「とりあえず〜」という言葉をよく使う。最終的に納品に至ったものですら、自分の中では感覚的に「とりあえずこんな感じですが」といった気持ちでいることが多い。つまり〆切が無ければ一生悩み続けることも
できかねない性分で、それは裏を返せば「まだまだやろうと思えばオレはやれますよ」という隠れたタカピー気質のようにも分析できるが、実際のところは「オレ的には限界なんですけど、ほかのひと的には分かりません」の心情である。どうも周りをカントクをはじめとする豪華クリエイター陣の方々に囲まれてるせいか、自分の限界点が途方もなくレベルの低いものだという認識があるのだ。いや、悲しいかな事実らしいんですけど。「デザイン」それ自体が商品として成立しない限り、デザインの良し悪しを決めるのはデザイナーでも観客でもない。それはそのデザイナーを起用した監督でありプロデューサーでありスポンサーであり重役の一人娘であり(<実話)、まとめてみればプロダクション全体である。だが、だからと言ってデザインの良否がプロダクションに責任転嫁できるかというと、決してそうではない。「いやーあれは監督の感覚が古くってしょうがなかったヨ」なんてイイワケは一見通用しそうだが、悪いモノに仕上げたのはやはりデザイナーの責任なのだ。なぜなら、もし決定的にプロダクションと意見が折り合わなければ、「自ら降板する」という選択だって残されているからだ。デザイナーは他にもゴマンといる。だからプロダクションには、デザイナーを選抜した責任だけがあるのだ。要するにデザイナーがアホだろうとセクハラやり放題だろうと、デザインがヘボかろうとパクリだろうと、プロダクション的にオッケーならば、すべてオッケーなはずなのだ。
「でも、オレじゃなければもっとイイモノができたかもしれない……」結局、いつもその言葉で自問は終わる。
普段はそうして作品が終わってようやく反省モードに入るのだが、今回は1つ納品するごとに自省回路が全開するというセンサー過敏状態だったため、かなり早い段階で「なんでオレなんだよ、オレじゃここ止まりだよ」と自分の限界を嘆くことも多かった。余談だが、人間は血糖値の上がるものばっか食ってるとこういう「どうせオレなんか」状態になりやすいらしいぞ。やっぱり野菜だ、野菜が必要なのだ。
『剛来(ゴウライ)』オリジナルデザイン

ところがここで問題が起こる。これまでの3回の反省で前述したように、悩みまくった結果としてデザイン作業の進行は大幅に遅れてきていた。しかも、ただ遅れただけなら平謝りに謝って〆切を伸ばしてもらえば済むだけだが(<本当はそんなことないです)、ここでオレ自身がスケジュール的にもう次の別の仕事に取り掛からないとマズいですマズいよどうしよう状態になってしまったのである。フリーランスという立場の性質上、こっちだけを立ててあっちを切り捨てるわけにはいかないんである。やってもいいけど後が怖いんである。
もちろん進行が遅れたのはこちらの責任であるので、なるべく多くの時間をデザインの方に費やしながら、一方ではクリクリとキカイに向かってCGの仕事をするという二重生活が始まった。こういう事が少ないわけではないが、それでも1日は24時間でオレという人間はたった一人だ。自ずと限界はある。心も荒む。だからそんな日々を重ねるにつれ、いつしか遅れの言い訳を考える回数も増えていく。非常に切実だが後ろ向きな考えに支配されちまうのである。弱く生きようとすれば、とことん弱く生きられちゃうのだ、人間は。
そんなわけで、同じ日のうちにデザイン頭とイラスト頭をコロコロと切り換えねばならない忙しさの中で、ただでさえ溝の浅い右脳に温存しておいたイメージやモチーフの数々はすっかり忘れ去られ、だがそれと同時に切羽詰まった時にしか出て来ないような火事場の馬鹿力みたいな強引な説得力でもって、4体を一気に仕上げることができたのだった。ん?結果的にオッケーになってますか?
さて四天王の一番手は「パワー格闘型」と位置付けられる『剛来』。いわゆる「マッチョ」体型好きなオレとしては最も得意とするところだが、それと同時に「好き」=「マンネリ」に陥りやすいネタでもある。なんとかそこから脱するために、いわゆる逆三角形マッチョとは異なる、スモウレスラーに近いゴリラ体型にすることを考えた上で、「肉体アクションが中心になるだろうから、身体にはなるべくディテールを入れないでおこう」と留意し、顔に大きなポイントを作ってシンプルなイメージにしてみた。ほら、こう書くとなんかすごく説得力あるでしょ。説得ついでに、実写の着ぐるみキャラでは困難な蹄っぽい足というのを試してみたかったので「これだけは譲れません」と書き添えてもみた。もう
やけっぱちである。実は監督からはこのプロポーションに対して、よりカッコ良いイメージへの修正(サイガードみたいだった)が来たのだが、やっぱり「譲れません」と要求を突っぱね、若干脚を長くしただけで完了とした。後に聞いた話で、この「初めての反抗」に監督は「ようやく篠原くんもノってきたようだ」と思ってくれたらしい。もちろん反抗にはそれなりに理由があるのだが、まさか「もういっぱいいっぱいだったから」とは今さら言えない。あ、言えないけど書いちゃったヨ。
一応それなりに好きなモノをまとめて、なおかつ反抗までして守ったものだけに愛着も深いが、結局ドクロのイメージとか使っちゃってるし新味はなかったですな。反省しとこう。フリだけ。
『惡弍(アグニ)』オリジナルデザイン

そんなわけで肩に大きな脚を付け、それを軸に巨大な大砲と本来なら脚にあたる部分に小型の砲筒を持つ変則体型にして、オレの中では多分に「メカっぽい」モチーフであるスリット状のモールドを全身に施すことで多少の生体メカっぽさも出してみた。要するにオレ的には「これは合成生物なのだきっと」という落とし込みである。そのため、このスリット以外にも目玉状のパーツなんかも追加し、毎度のごとく「よく分からんし複雑すぎる」感じになってしまったのだった。そして毎度のごとく反省。 その後「大砲後部のカタツムリ部分がかわいく見える」という理由で変更の指示が来たのだが、ここはオレ的にはマガジン的な役割のパーツであって、カタツムリの殻以外にそれらしいモチーフを見つけることができなかったので、例によって「譲れません」と突っぱねたのだが、ここは監督も譲れなかったらしく、結局銃口の形状と共にアニメ用設定を起こす段階で修正が入ったようだ。自分の引き出しの少なさを棚に上げておいて、まるで逆ギレのようだったと猛反省してます、今は。
「脚にあたる部分の砲筒が回転して腕が出て来る」というアイデアは、ラフ段階で一度消えたものの最終的に復活し、結果的には「世界中で最も有名な映画シリーズの最新にして最古のエピソード」に出て来るイジワルレーサーに似てしまったんだが、ぶっちゃけた話をしてしまうと、『〜定光』に登場する流刑体の多くは、かつて80年代にレベル社が展開していたアクションフィギュアシリーズ『POWER LORDS』のエイリアンにイメージソースを求めている。パクリって言うと聞こえが悪いから
リスペクトってことですか。これは1回目に書いた大畑監督の「フィギュアになるといいねぇ」発言を受けた瞬間に「ああ、あんな感じになるのかな」とオレの頭によぎったもので、とりあえずモノを脇に置いたりはせずに頭に残ったイメージだけ参考にした程度なんだが、後で見てみたらかなり似てるのとかありました。詳しく書くと死にたくなるくらい恥ずかしいので、気になる人は調べてみれ。いいんだよ、これが(<って開き直ってどうする)。
『流牙(ルガ)』オリジナルデザイン

で、なんとか『剥斬』と違うところで苦し紛れに鳥のモチーフを入れてラフを出したら、これが意外と監督には好評だったので、調子にのって一気に仕上げた。ただ、ラフでは腕がムチ状だったのだが、完全に羽にする指示が出たので、逆にそれ以外の部分からは鳥のイメージを減らすようにして、普通の「鳥男」にならないようにしている。でもよくよく見直してみると、アバラ骨の浮き出たところとかは結局『剥斬』に戻ってるじゃん?だめじゃん?
ちなみに色に関しては迷うことなく青。なんでかというと、他の流刑体で使ってない色はこれだけだったからで、つまりこれが着彩は最後だったわけですな。欲を出して水色までグラデーションで使ってるのは、ただの貧乏性です。
『依弩(イド)』オリジナルデザイン

決定デザインを前にしちゃうとそんな感じだが、実は途中段階ではかなり迷走したところもあって、それは間違いなくキャラクター的な重要度と「ホルモン野郎」(<準備稿段階では定光がこう呼ぶ台詞があった。ちょっと残念)の外見とのギャップを自分の中で埋められずにいたからで、事実、自主的にボツにしたものの多くは人間的なパーツやマントがあったりして、どことなく大ボス風の要素が加わっていたりした。いや、ボスといえばマントなんですよ、オレ的宇宙では。
最終的な監督の要望ラフを前に色々考えた結果、「もしかしたら実写ならこれでオッケーかもしれないけど、アニメだと違うのかも」と思い直し、気持ち悪い部分をなるべく減らしたり隠したりするようにして、純度高めたところで時間切れ完成となった。実は提出した完成デザインすら「でもやっぱり違うかも」と思ってたんだが、オンエアで動いてるの見てようやく「やっぱりこれだったな」と思えるに至ったのである。なんか一番アニメっぽくなってる気がした。それもなんだかなぁ。
この反省会を読んだ多くの方が「こうして言い訳めいたことを書かねばならんほどシノハラは批判に対してヘコんでるらしい」と思われたかもしれないが、実は今回、うっすらと聞こえてきてしまう批判以外は、意図的に排除してきたんである。「掲示板とか、あんまし見ない方がいいヨ」というありがたい忠告が、否応なしにその内容があまりありがたくないと想像するに易かったこともあるんだが、排除したのは決してそのためではない。今回に限らず、いっつもそうなのだ。かなり小心者なオレだが、意外と視聴者の批判とかいうのには心を動かされないんである。もちろん「商品」としての作品や関連商品の売れ行きには一般的な評価も指針となるのだろうが、それが必ずしもイコールでないことも知っている。だから「ふうん」ぐらいにしか思わない。よっぽどヒドい事とか言われるとムカっ腹も立つし噛み付きたくもなるが、そこで反省したりは絶対しないのだ。いや、「アレ見たら死にたくなった」とか言われたらちょっと考えますけども。
反省は常に自分の内から現れる。しかも一度出てしまうと、無尽蔵にあふれかえる。今回は特に、監督の大畑さんや実際にアニメーション制作にあたった方々、特にキャラデザの菊池さんや制作の飯嶋さん、そしてオレの珍妙で稚拙なキャラクターを実際に描いて下さったアニメーターの方々に対する反省が、もうやってる最中から拭いても拭いても濡れちゃってじゅん、みたいな感じで常々申し訳ないと思い続けていたのである。決して他人にとやかく言われたからではなく、「どこかで謝っておかないと生きていけない」と思ったから始めたものなのだ。つまり謝るということは当然これからも生きていこうと思ってるわけで、実は相変わらず「変なジャケット着て声優の女の子はべらせたキャデラックで特写inサイパン」みたいなことを狙ってるのかもしれん。自分でもそれがかっこいいのか、よく分からなくなって来てるけどな。だからもし「次」があれば、その時初めてオレの反省が終わるのだ。もちろん、次がなければ反省したまま死ぬだけなんだが。
そんなわけで、まさか「これからのオレを見てくれ」なんて言うつもりはない。誰が見てようと見てまいと、自分のできる精一杯の誠意こそが常に人生のファイナルアンサーなのだ。
……ってこんな締めでいいわけないので、最後に一言。どうもいたらなくてすいませんでした。>関係各位樣