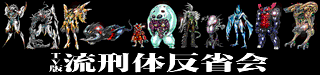
第3反省〜涅槃と解脱篇(4、5話)
一筆完全燃焼
新たな作品作りに取り組む時、人は誰でもそこで何かを挑むものである。既に行き着くところまで到達してしまって、向上心のホコ先がついついスカイダイビングとかフェラーリとかに逸れてしまった巨匠と呼ばれる人(<特定人物のことじゃないです念のため)ならともかく、未だ発展途上、ぶっちゃけた話まだ駆け出しのペーペーであるオレなどにとっては、何かを挑まざるをえない状況が常にあるのである。そしてたいていの場合、デザイナーという職業人が挑む野望というのはこれに終始する。つまり−
「誰も見たことないような斬新なものを創りたい」というものである。
もちろんウルトラマンや仮面ライダーに匹敵する新しい何かをヒョコヒョコと創り出せるものではない。デザインするだけならともかく、それをキャラクターとして世に出して認知されてエポックとして確立させて、おまけに版権で一生メシが食っていけるようになるのには、やはりそれ相応の実力と、そしてかなりの幸運が必要になる。加えて言うなら一話限りの悪怪獣のデザインなどと言うのはたいていの場合が「買い取り」(デザイナーがキャラクターの権利を製作者に譲渡すること。原稿料はその分良くなるが、稀に後で化けると泣くこともある。ただし成田先生みたいなのはほんとに稀)なので、長者番付に名前を列ねたり『TIME』の表紙を飾ることなんてのは夢のまた夢の更に特急に乗り換えて2時間後着、みたいなものなのである。それよりは当たり障りのないデザインを大量にこなして、夕食のおかずをよりゴージャスにすることを考えた方が賢いのだ。むしろそうやって自らを確立させていけば、いつかきっと幸運な巡り合わせも訪れるのである。
「だが、しかし。だがしかーし!」
と叫ぶのは、オレの中のアストロ魂なのだろうか。とにかく発展途上、特に技術的にもセンス的にも貧しいデザイナーが採り得る最大の挑戦であり最高の誠意とは「一筆完全燃焼」なのだった。つまりひと筆動かすたびに「これでいいか?これは斬新か?」と常に問い続ける姿勢である。当然そうやって描いたとしても、最終的に出来上がったものを見て「ワイアール星人じゃん」とか思ってしまったら敗北であるから、それを認めないうちにグシャグシャに丸めてゴミ箱へ捨てるのだ。
では、それは何故なのか?自分のためではない。かつて自分がそうだったように、テレビマガジンのグラビアを穴が空くほど見つめたり、意味もなく細かくマス目を切った紙に怪獣の名前を書き出して下敷きにはさんで持ち歩いたり、番組を見ながら出ている怪獣をスケッチして私家製怪獣辞典を作ったりしている、だれかのためである。そんなだれかがきっと今でも日本に3人ぐらいはいると信じているからである。そして「実はスモウボーマを見てこの世界を目指しました」とか言ってくれるだれかが現れることを期待しているのである。もし現れなかったら、それを時代や社会のせいにする負け犬の老人になればいいのだ。
そんなわけで、『〜定光』においても、その姿勢が崩れることはなかった。しかも監督の大畑さんは『地球戦隊ファイブマン』で同じデザイナーとして参加していながらも、初見の時に「『鋼の鬼』の大畑さんに会った!『飛影』の大畑さんに!」と日記に書いたほど(ちょい誇張)圧倒的にレベルもスキルも上の人なので、
普段の2割増の全力で挑もう、いや挑まねばならないと心に誓ったのであった。そしてそれは決して苦痛ではなく、なぜならその裏には、ええい言ってしまおう「これで新風を巻き起こしてアニメ業界をオレが牛耳ってやるぜ。変なデザインのジャケット着て隣に声優の女の子とかはべらせてアニメージュで特写されてやるぜうっしっし」などという、とんでもない野望を抱いていたからなのだった。もちろんそんなことは、夢の中で見た夢の中でさえ榎本加奈子に「バッカじゃないの?」と突っ込まれても当然の、妄想以外のナニモノでもなかったのだが。
さて、ご存じの方も多いと思うが、「一試合完全燃焼」を果たしたアストロ球団は、結局日本のプロ野球界には居られなくなっちゃうのである。なにしろプロ野球は年間百数十試合こなすわけだから。それもプロのプロたる所以なのですな。
『後武(ゴブ)』オリジナルデザイン

ギャグ編というのは毛嫌いする人もいるかもしれないが、シリアスなシリーズ中においては息抜きであり、作り手側にしてみれば、ふと忘れていたことを思い出す絶好の機会にもなる。5話のプロットが遅れていたこともあって、この2体の作業が早くもシリーズでの折り返しということになり、1話の『剥斬』での反省を踏まえた上で、ラフスケッチの作業を慎重に行うことにした。
その念頭にあったのは「決してヒト型でなくてもいいのでは?」という事だった。「流刑体とは犯罪者であり、罪を罪となすためには罪人には知性がなければならないだろう」という意味で、無意識のうちに「流刑体は人型」という固定観念(ちなみに『駆崙』は最初から「バイクに寄生する」という注釈が付いていた)が生じていたオレは、出来上がった『剥斬』を(もちろん純粋なヒトのカタチはしていないにしろ)手があり足があって〜というヒトの構造を模したものにしていたのである。アクション時における作画のし易さから、ヒト型の方が望ましいというアニメーション的な要望はあるにしても、各器官や骨格の構造を変えることで斬新なシルエットは生み出せるはずだった。いや、できる。しかも身体の大きさと性格がアンバランスなこの2体には、うってつけのコンセプトかもしれない。いや、まさに相応しい。などと、人間は少し心に余裕ができると、ついつい要らぬ欲が出てしまうのだ。
結果的にヒトの構造自体はそのままだが、顔や骨格の付き方にヒト以外のものを使用したラフを各々3点ずつ作ったところで監督チェックを受ける。『厘隠』のラフの中にはカバの顔をまんま付けたりしたものもあったのだが、これはぶっちゃけた話が「捨て案」というものであって、デザインを提示する時のテクニックの一つなのだ。すなわち最低3点のデザインを用意して、自分のやりたいことが反映されている順に「お薦め」「キープ」「捨て」という3つのグレードを決める(別に決めなくても自ずと決まってしまうものなのだが)。この「捨て」というのは「自分ではどうかと思うけど他人の意見も聞いてみたい」時や、純粋に「お薦め」の引き立て役となったりするもので、あからさまにオーソドックスなものや、あるいは逆に突飛なものにすることが多い。実は『厘隠』の方では、「お薦め」のラフが要求の一つである「岩に擬態する」というのを表現していなかったため、敢えてそういうのを混ぜていたのだった。実力はないくせにキャリアだけは長いから、変に小ずるいとこはあるわけだね。
その甲斐もあってか『厘隠』はまさに「お薦め」の1枚が選ばれたのだが、ところが逆に『後武』の方は「捨て案」にしたつもりだった非常にオーソドックスなものが選ばれ、しかも監督から「これいいねぇ」とまで言われてしまったのである。まさに急転直下。思わぬしっぺ返しであった。
『厘隠(リイン)』オリジナルデザイン

そんな時にでも容赦なくステジオディーンの飯嶋さんからは電話があって、それが鬼のような催促であればちゃぶ台をひっくり返して「ああ辞めてやるぜチッ」などと捨て台詞も吐けるのだが、電話口で「そうですか…いつぐらいになりますか…?」と次第に細くなる声を聞いていると、どことなく草食動物のそれを思わせる飯嶋さんの瞳がようく見ると涙でいっぱい、みたいな姿がうっかり想像されてしまい、ついつい「じゃあ来週アタマまでに〜」と言わざるをえなくなるのであった。いや、あれは高度なテクだと思うんですが、どうなんでしょう。
とりあえず再度ラフを見つめ直して色々と考えた結果、「これは表情を優先させたのだろう」という結論に達した。しかし「表情を分かり易くする」というのは、引いては「受け入れられ易いキャラクターにする」ということであり、それは実は「斬新なもの、見たことないようなもの」と正反対のところにあるのだ。また「表情が変化する」ことは、一枚のデザイン画を絵として完成させたいという自分の仕事の仕方とも相容れないものでもあった。
この結論は、元々オレ自身が無表情なキャラクターを好むこともあって、それを含めて確かにある意味で
むろん頭で理解していても、その理念と自分なりに譲れないものとの折り合いを付け、それが紙の上のイメージにまとまるには相当時間もかかって、事実この『後武』は完成までに数十枚も同じような絵を描いた。時間がかかった分それなりに手が加わって、小さい身体の割にディテールとか増えて、しかも実はそれが規則的なパターンで出来てて作画しにくかろう、まぁいいか適当にゴマカしてもらえば、みたいな感じになってしまったという小反省もあるんだが、たまにこういうターニングポイントがあるからこそ、新しい意欲が湧いて来るのも事実。そういえばその前のターニングポイントはカクレンジャーの『コナキジジイ』だったなぁと思い出してもみたり。あれで「ああもう戦隊は辞めよう」と思ったのだ。しみじみ。
とか偉そうに書いてはみたものの、結局あの時監督にちょこっと相談しとけばあっさり解決したのだろう。そこんとこは反省もしきりなんですが。
『弾喪(ダンソウ)』オリジナルデザイン

いやもうこれが作業としてはやたらスムーズで、というのも前回の『後武』で相当悩み切った後だったから、「別にヒト体型でいいじゃん、ニラサワさんっぽくてもいいじゃん、かっこ良ければすべてオッケーだ」みたいに吹っ切れた状態で描けたからなのだった。ポンチョ風のシルエットや革パン風の色使い等のあからさまな既存イメージの引用が、このまま戦隊に出てもおかしくない、いわゆるオレデザインの王道みたいな感じだが、それでもかっこ良ければいいのだとチョーシぶっこいてたんである。
このように、「かっこ良い」というのは「好ましい」ということと同意で、裏返せばまったく新味がないのである。
後に『〜定光』関係の取材の折に監督から聞いた話だが、この『弾喪』を見て音響関係のスタッフが「あの『セーロス』が〜」と言ったそうである。言わずもがな『セーロス』はニラサワさんの手がけた『AMON』のキャラクターだ。なんか今さらになって猛反省。もう泣いちゃいそう。あ。